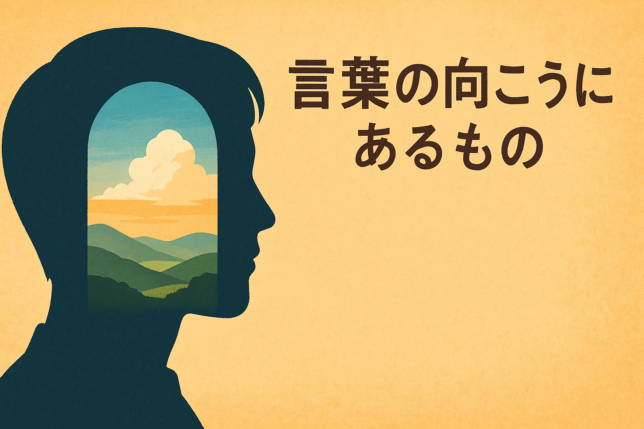
Do you pour everything into your work?
Or maybe… it’s better to pour everything into your life instead?
言葉の向こうにあるもの
数日前、私たちの会社で定例のGMがありました。そこでゲストスピーカーの方が、おそらく若いメンバーに向けてだと思うのですがこんなメッセージを送ってくださいました。
「皆さんが一生懸命仕事をすれば、会社は必ず答えてくれます。」
その場にいた一人として力強く、誠実な言葉だなーと素直に思いました。その後、私は代表としてお礼の気持ちを述べると共に私も素直に思いをお返ししました次のように。
皆さんへの力強いメッセージどうもありがとうございました。そして、お言葉ではありますが、私は仕事についてはこう思うのです。
「一生懸命仕事をする前に、皆さんには一生懸命人生を生きてほしい」と。
決してかっこつけてるわけやないです。なぜなら、一生懸命に人生を生きていれば、結果として必ず良い仕事ができているはずだからです。
仕事が目的なのではなく、人生が目的であってほしい、仕事はその人生の結果であってほしい。
そして、もしも――いや、「もしも」ではなく、「きっと」と言いたい。
この会社が正しい仕事をしている会社なのだとしたら、
みなさんが一生懸命に生きていること、そのことが必ず価値ある仕事になっているはずだからです。
正しい仕事をすることが正しい人生になるとは限らない。
しかし、正しい人生は正しい仕事となるのです。
正直なところ、どれだけ皆さんに伝わったのかは、その場では全く分かりませんでした。
ところが数日後、DLC(日報のようなもの)の中で、ある外国籍のメンバーがこう記してくれていたのです。
「人は“一生懸命働く”のではなく“一生懸命生きる”べきだ」という言葉が印象に残りました。
こう、書いてくれていたのです。たったワンセンテンスです、むちゃくちゃ短い一節ですけど私は好意的に解釈します、彼は実に日本語を学びながら、私の言葉の「奥」を感じ取ってくれたんだなーと。
その事実が何よりも嬉しく何よりも力強く私の心に響きました。
あらためて強く思いました。
この場を借りて、どうしても伝えたい感謝の言葉があります。
「私たちの言葉、日本語を学んでくれて本当にありがとうございます」
これは形式的なお礼ではありません。私のどちらかというと早口の日本語を理解してくれたのは彼が日本語を勉強してくれているからです。私はこういった話をする時にはこの日本語は日本語学習者に通じるだろうかと単語の一つひとつを意識しながら話しています。周りから見るとまたきのわきさん興奮して話してるわ、いつもエキサイティングねと思われていると思いますが、これでも本人は割と冷静なんですよ。
さて、そんな彼らは日々の業務の中で、日本語で会話をし、日本語で資料を読み(エンジニアなので実際は英語が多いでしょうね)、日本語の文化に触れようとしてくれている。その努力と姿勢に、私は敬意と感謝の念を抱かずにはいられません。
なぜなら、なぜなら。
少し日本語の体系に踏み込みますが、日本語は決して習得しやすい言語ではないからです。アメリカ国務省の言語研究機関(FSI: Foreign Service Institute)によれば、日本語は英語話者にとって最も習得が難しい言語のひとつとされています。上のページをずーっとスクロールして一番下までくると日本語がアラビック、カントニーズ、コリアンと並んでレベル5となっているのに気づかれるでしょう。しかもジャパニーズにはアスタリスクが付いてます。そしてそのアスタリスクの注釈は、”Languages preceded by asterisks are usually more difficult for native English speakers to learn than other languages in the same category.”です。同じカテゴリに入っててもこの言語はもう一つ難しいでと指摘されちゃってます。という事は日本語は世界で1番難解な言語だって言うことですよねもちろんそれはNative English Speakerにとってですけど。
英語を母語とする人(この場合には外交官、つまりちょっとだけ賢い人かも知れない人たち)が、日常的な会話ができるレベルに到達するまでに必要とされる学習時間は、およそ2200時間以上なんです!
2200時間あったらあなた何します?
私は人生やり直します!
これは、フランス語やスペイン語とかのヨーロッパ言語(約600~750時間)と比べて、およそ3倍の学習量を要するということです。
その難しさにはいくつかの理由があります。まず、よく知られたところで日本語は三つの文字体系(ひらがな・カタカナ・漢字)を使い分けます。最近は訳のわからん英単語も入ってきます。
さらに漢字は一文字に対して複数の読み方が存在し、同じ語でも文脈によって意味が変わることがあります。また、語順が英語と異なり、主語や目的語が省略されることも多いため、意味の理解には背景知識や文脈の読み取りが不可欠です。
日本語には敬語やあいまいな表現が多く含まれます。正解が一つではなく、「ふさわしい言い方」は相手や場面によって異なります。これは、日本語の豊かさであると同時に、学習者にとって非常に高度なバランス感覚を求める要素でもあります、時には相当のストレスも与えてるんじゃないかと時々ハラハラします。
だからこそ、私は「日本語を学ぶ」という行為そのものに、深い価値を感じています。それは単に語学スキルを身につけるということではありません。その背後には日本人の思考のリズムや、社会のしくみ、文化的な感受性に歩み寄る姿勢があると私は受け取っています。つまりこの学習の過酷さを乗り越えてくる人たちって本気で日本や日本人のこと好きなんちゃう?と。
言語は文化の鏡です。「ありがとう」や「いただきます」といった言葉に込められた感情や意味を理解しようとするとき、その人はもう文化の中に入り始めているのでしょう。そして、そうした文化に自ら歩み入ってくれている人たちと一緒に働けることに、私は本当に誇りとともに喜びを感じているのです。
言語が生む知性という風景
世間でもそうですが、当たり前のように私たちの会社でAIの2文字が会話にでないことはありません。彼らの進化によって私たちは今まさに「言語とは何か」という問いを、これまで以上に深く見つめ直す時代に生きています。特にChatGPTに代表される大規模言語モデル(LLM)の登場は、言葉の可能性と、思考の本質について多くの示唆を与えてくれます。
こうしたAIは、膨大な文章データを学習して、私たちと自然に対話できるような能力を持つに至りました。以前は、これらのモデルは単に「次に来る言葉を予測して並べているにすぎない」と説明されることが多くありました。確かに、基本的な仕組みは確率的な言語生成――言い換えれば「これまでの言葉の流れに照らして、もっとも可能性の高い言葉を続ける」というものでした。
しかし、最近のトレンドは、Chain-of-Thought(思考の連鎖)ですよね。これは、質問に対してただ答えを返すのではなく、「まず状況を整理し、それから一歩ずつ論理を進めて結論を導く」という、人間の思考に近い応答の形式です。受けこたえを見ているとそんな感じに見えるので不思議です。今後はもうこの推論モデルのみになっていくのでしょうね。作画で用いられているデヒュージョンモデル、いわゆる拡散モデルも面白そうですが、ここではこれ以上話は広げません、まずは言葉への感謝です。
こうした応答は、あらかじめAIに「推論を行え」と明示的に指示した場合に限らず、文脈に応じて自然に現れることすらあります。まるでAIが“考えている”かのように見えるのは、こうした段階的処理が言語の中に埋め込まれていて、AIがそのパターンをたどっているからですよね。だから、一見考えているように見えますね。
つまり、AIは意味を理解しているわけではありません。
チャッピーにお前考えてんのか、意識あんのかと聞いても決してそうは答えませんね、そんなんあらしまへんととぼけられて終わりです。
けれども、言葉というものの中に含まれている「思考の構造」そのものを模倣するようになってきているのは確かですよね。模倣こそ意識やないかい!意識の正体は模倣やで兄ちゃんという声は置いといて、そしてその結果として、私たち人間の目には、そこにあたかも思考や感情が宿っているかのような応答が現れているように映ります。
この現象は、最近はあまり人々の口にはのぼってきませんが「創発(エマージェンス)」という言葉でも説明されます。そういえば2年ちょっと前ChatGPTの3.5がリリースされた時、なんでこんなことが起きるんやなんでやなんでやそうや創発現象やってとこで懐かしい言葉です。
余談ですが私が初めてChatGPTに触れたのは2023年の3月、沖縄の那覇から北の本部町に向かって国道58号線(海の上を走っているので珍しい国道)をチャリンコで走らせている時でした、YouTube聴きながら耳に入ってきたChatGPT3.5の解説を聞いてしばらくは国道でそのまま動けなくなったの覚えてます。一体何が起きたんだと。そして翌日目的地についてそこでいつものように酒飲むわけですがもうその時はお互いにチャットGPTのことばかりでした、これは何なんだこれは何なんだと3人でしたけど採用の面談ではありましたが、なんだか話題はChatGPTだったのよく覚えてます。
ただ、今はもうなんでやってゆうことはあまり問われなくなってきてるのはなぜなんでしょうかね。いまだに飛行機はなぜ飛ぶのかわからないままに飛行機を飛ばしているような感覚がないでもありませんね。
個々の要素は単純であっても、それらが一定のパターンで組み合わさることで、予想を超えたふるまいが現れるという現象です。AIの内部には「心」も「理解」もありませんが、言語という複雑で濃密な構造体を学習し続けることで、知性のようなものが出現してしまってます。
ここで、私たちが立ち止まって考えたいのは、「では、人間にとっての言語とは何か?」という問いです。
私たちもまた、言葉によって思考しています。何かを考えるとき、「うまく言葉にできない」という状態は、まだ思考がまとまりきっていないことの表れです。そして「言葉にできた」ときには、「やっとわかった」という実感が訪れる。つまり、言語は思考の表現手段であると同時に、思考そのものを形づくっている土台なのです。わかった!ということは分けることができた、つまりなんだかわからないものが言葉によってこれとこれと言う具合に分けることができた、これがわかった、つまり理解できたっていうことですよね。言葉という大地に着陸できたわけです。
この視点から見れば、日本語を学ぶということも、ただ新しい語彙を覚えるという以上に、日本語という思考様式に触れ、取り込もうとする営みであることがわかります。言葉の順序、含み、曖昧さの扱い、敬意の表現――そうしたものを理解し、使いこなそうとする過程には、自分の内面を拡張していくような、知的な変化が伴います。
外国籍の仲間たちが日本語を学びながら、戸惑い、考え、工夫してくれている様子を見るたびに、私は「言葉を学ぶとは、まさに新しい知性を育てることなのだ」と感じます。
AIが言語によって知性を生み出し始めているように、私たち人間もまた、言語によって自らの知性を育て、文化を広げてきました。その意味で、日本語を学んでくれている仲間たちは、ただ“日本語が使えるようになる”のではなく、文化を通して育まれる思考の営みに、自らを巻き込んでくれているのです。
それは、私たち自身が当たり前に使っている言葉や文化を、もう一度見つめ直す機会を与えてくれる。異なる言語背景を持つ仲間と働くことは、異なる知性と出会い直すことでもあるのだと思います。
日本語を学ぶということは、ただ日本語を「話せるようになる」ことではありません。
その言語の背後にある思考様式、価値観、感受性に触れ、学び、自らに取り込んでいくことなのです。
文化と働く。
私たちの会社のフィロソフィーは、「文化を愛し、教養を育む」です。
ずいぶんと前に掲げたものですが、今、改めて思うと私たちは彼らと一緒に働くことで日々それを実践しているのではないかと実感します。この理念は、外国籍の仲間たちが日本語を学びながら実践してくれている姿そのものに表れています。
これは、言ってみれば文化を媒介とした、相互の知性の育成の現場とも言えると思います。
文化を滅ぼすには、言語を断てばいい
これは、民族浄化の手段として歴史の中で語り継がれてきた言葉です。
言語が失われるとき、文化もまた静かに消えていく――これは恐ろしい現実ですが、同時に言語がいかに文化の根幹をなしているかを物語る言葉でもあります。
だからこそ、日本語を学ぶということは、文化の継承であり、共生への参加なのです。
そして、これからの社会は、AIによって生活や仕事の構造が劇的に変わっていくでしょう。
そのとき重要になるのは、「異なる知性」とどう向き合うかです。
言語や文化の違いを越えて関係を築こうとすること――
それは、まさにDEI(Diversity, Equity, and Inclusion)の実践であり、
未来社会において最も重要な資質の一つであると私は考えます。
だからこそ、私はあらためて強く言いたいのです。
「私たちのことば日本語を学んでくれて、本当にありがとう。」
DEIは、Diversity(多様性)、Equity(公正性)、Inclusion(包括性)の頭文字。
Diversity(多様性):個人や集団の間に存在するさまざまな違いを指します。これには、年齢、性別、性的指向、人種、国籍、民族、宗教、障がいの有無など、多岐にわたる要素が含まれます。
Equity(公正性):すべての人が平等な結果を得られるよう、個々のニーズに応じた支援や調整を行うことを意味します。全員に同じ条件を提供するのではなく、一人ひとりの状況や背景を考慮し、公平な機会を提供することが重要とされています。
Inclusion(包括性):多様な個人が組織や社会の一員として受け入れられ、積極的に参加し、貢献できる環境を整えることを指します。
現代社会において、DEIの推進は単なる倫理的な課題にとどまらず、組織のパフォーマンス向上やイノベーションの促進にも寄与するとされています。多様なバックグラウンドを持つ人々が集まることで、新しい視点やアイデアが生まれ、組織全体の競争力が高まると考えられています。パーパス経営的側面ですね。
しかし、DEIの推進には課題も伴います。2025年1月、アメリカのトランプ大統領は、連邦政府内外のDEIプログラムを解体するための大統領令に署名しました。これにより、DEI関連の取り組みが一部で後退する動きも見られます。
私たちの会社にはJLPTの試験に積極的に挑戦し高得点をマークしているメンバーがいます。そこであまり世の中的には知られていないJLPTの試験問題を引用させていただきます、N1レベルの試験問題です。
さて、日本人のあなた、日本語を母語とされているあなたいけますか?
次の言葉の使い方として最もよいものを、1 • 2 • 3 • 4 から一つ選びなさい。
「いたわる」
1 弱い立場の人をいたわるのは大切なことです。
2 山田さんはこれまでの努力をいたわってくれました。
3 母は孫が遊びに来たら、いつもいたわっていました。
4 政治家は国民の生活をいたわるべきです。
「キャリア」
1 その分野のキャリアになるには、長い間の努力が必要だ。
2 先月賞を取ったあの歌手のキャリアは苦労続きだったそうだ。
3 昨日、異動の発表があって、兄のキャリアは部長になった。
4 彼のキャリアはそれほど長くないが、この仕事をよく理解している。
次の文の( )に入れるのに最も適当なものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。
人に( )されたことを、いつまでも根に持っていても、前に進めない。
1.辱め 2.罵倒 3.中傷 4.非難
次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして、最もよいものを1 ・2·3·4から一つ選びなさい。
歴史の教科書には、有史以来の「大事件」が山ほど取り上げられている。歴史の特色は、歴史が「起こったこと」の連続として書かれていることである。しかし、人間の毎日の活動の集積が歴史だとすれば、歴史の大部分は「起こったこと」の裏にある「なにも起こらなかったこと」で埋め尽くされていることに気づく。
われわれの日常生活を考えれば、事件などほとんど起こらない。もっといえば、われわれは毎日、「事件」が起こらないように注意して生活している。車を運転するときには人にぶつけないように、料理するときには包丁で手を切らないように、それで当たり前であろう。
そう考えると、歴史の教科書の書き方はきわめておかしいという気がしてくる。
もちろん、「なにも起こらなかったこと」をつなげても、歴史は書けないであろう。
しかし「起こったこと」だけをつないだ歴史は、なにかが起こらないようにするために日常的に払われている努力を無視している。
その意味では、①現実を誤解させる恐れが強い。ともあれ人間は「起こったこと」のほうを好む。ジャーナリズムをみれば、それがわかるであろう。歴史とジャーナリズムは、できごとの連続として世界をみる点で、根本的に似たもの同士である。なにかが起こらないようにすることは、意外に大きな努力がいる。それが地味な努力ということである。歴史もジャーナリズムも、それを基本的に評価しない点で共通している。
医学の領域でも、これと同じように、予防医学は二の次、三の次におかれる。手術や投薬で病気が治れば、医者は感謝される。「起こらなかった」病気に、治療費を払う患者はいない。やったことに対する報酬で成り立つ世界、つまり経済中心の世界のおかしさは、そこにある。
②そこでは予防に人気がないのは当然である。なにかが起こらないようにするための努力が大切だと気づくのは、なにかが起こってしまってからである。医者の忠告を無視して病気になれば、あのときいうことを聞いておけばよかったと思う。BSE (牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病)の牛が出たとわかってから、飼料の原料をきちんと管理しておくべきだったという話になる。バブル期(注l) にマネーゲームに手を出して損をした企業は、本業だけに精を出していた企業をうらやむ。
(養老孟司『いちばん大事なこと』による)
(注1) バブル期:土地や株が異常に値上がりする経済状況の時期
①現実を誤解させる恐れが強いとあるが、どのような誤解を生むか。
1 歴史に書かれていることは順番に連続して起こったことだと思われる誤解
2 歴史に書かれないわれわれの日常生活には歴史的価値が無いと思われる誤解
3 「起こったこと」以上に「起こらなかったこと」のほうが大事だと思う誤解
4 「起こらなかったこと」はどうやっても歴史に書けないと思ってしまう誤解
②そこはどこか。
1 何かが起こらないようにいつも地味な努力が払われている世界
2 「事件」より「何も起こらなかったこと」で埋め尽くされた世界
3 「起こったこと」「やったこと」だけが注目され評価される世界
4 何かが起こって、何も起こらないことの大切さに気づいた世界
⚫︎筆者が言っている「起こらなかったこと」の例はどれか。
1 飼料の原料を厳しく管理していたからB S E は出なかった。
2 重い病気の患者を手術することなく薬で治すことができた。
3 もともとお金が無いから損をすることもなく、安心である。
4 車を運転していて事故に遭ったが、自分は悪くはなかった。
⚫︎この文章で筆者が言いたいことは何か。
1.「起こったこと」の連続として書かれている歴史は、その裏にある「起こらなかったこと」を忘れている。真実は書かれていないことの中にあるのである。
2.「起こらなかったこと」は注目も評価もされないが、実は起こらないようにするには大きな努力が払われている。私たちはその大切さに気づくべきである。
3. 歴史とジャーナリズムは、「事件」が起こらない私たちの毎日の日常生活のことは取り上げないが、もっと注目しきちんと伝えていくべきではないか。
4. 人々は「起こったこと」のほうを好むから、歴史とジャーナリズムは「事件」を追うことになるが、経済中心の世界ではそれは仕方のないことである。
